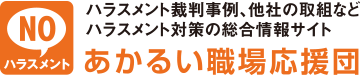- 精神的な攻撃型
- パワハラと認められなかったもの・パワハラを受けた人にも問題が認めれた裁判例
【第7回】
パワハラの事実認定と法的評価について
三洋電機コンシューマエレクトロニクス事件
広島高裁松江支部平成21.5.22
労判987号29頁
はじめに
職場のパワーハラスメントの典型例として、よく挙げられるのが、上司等による「ひどい暴言」です。本HPにおける「職場のパワーハラスメントの類型」においても、類型の1つとして挙げられおり、原則として職場において許されない行為であることは明らかといえます。(職場のパワーハラスメントの類型)
その一方、当該パワハラをめぐり実務対応上、極めて難しい課題の1つとして事実認定と法的評価の問題があります。例えば加害行為を働いたとされる社員が「ひどい暴言」を否定した場合、会社側が調査に乗り出しても「言った言わない」の水掛け論に陥る危険があります。そのためか近年、被害社員側が会社に無断でICレコーダー等によって上司の言動を秘密録音するケースが増えているようですが、このような秘密録音によるパワハラの訴えに対し、如何なる事実認定と法的評価を行うべきでしょうか。以下では裁判例を紹介し、同問題を解説します。
事案の概要
控訴人YはY社島根工場の半導体製造部門の業績が悪化し、余剰人員が発生したことから、他の部門への生産応援、異動のほか、転進支援制度の緩和等を行っていました。Xもマルチメディア部門に生産応援のため派遣されていたところ、平成18年6月末には同部門も生産終了することとなり、Y社では会社内部での配置換えの他、県外会社への出向等を検討していました。
そのような中、平成18年5月10日、Xは勤務終了後、女子ロッカーにおいて、同僚C、Dに対して「同僚Aが会社のお金を何億も使い込んで、こっちに飛ばされただけぇ、乙山課長も迷惑しとるだけぇ」という旨の話をしたとされます。これを聞きつけたAは事実無根の中傷であるとし、Y会社B課長、人事担当者Y1、Y2等に対して相談を行い、Y1・Y2らが社内調査を行ったところ、同僚C、DからXによる中傷発言があった事が確認されましたが、X本人は事実関係を否定しました。
その後、同年6月16日には、XはY会社取締役Eに対して直接、携帯電話に電話をかけ、以下の申し立てを行いました。①工場においてサンプルの不正出荷をしている社員がいる、②私を不当に辞めさせようと、人事等が圧力をかけてくる、③契約社員を辞めさせようと、県外出向を強要しようとしている、④社員の中には、人事担当者を「ドスで刺す」などの過激な発言をする者がいる等。EはY1に対して、Xからの申立内容を伝えるとともに、Xの話は不適切な内容なのでよく話を聞いて注意するよう伝えました。
Y1らは同日午後4時55分頃にXを人事課会議室に呼び出し、B課長とともに面談を実施したところ、Xは終始ふて腐れたような態度で横を向いていました。これにY1が腹を立て、感情的になり、以下の発言を行ったものです。なおXは同面談時、Y社に無断で当該音声をボイスレコーダーで秘密録音しており、これを裁判所にCD—Rで証拠として提出しています。
①Xが裁判所に訴えると述べたことに対して 「正義心か知らないけども、会社のやることを妨害して何が楽しいんだ。あなたはよかれと思ってやっているかもわからんけども、大変な迷惑だ、会社にとっては。そのことがわからんのか。」
②Xが誹謗中傷の事実を否定したことに対して 「言ったんだ。ちゃんと証拠取れているから。・・もう、出るとこに出ようか。民事に訴えようか。あなたは完全に負けるぞ、名誉毀損で。あなたがやっていることは犯罪だぞ。」
③県外出向の件について 「今回の福知山に行く件は、あなたが一切口を挟まないでくれ。迷惑だ。」
④その他 「前回のことといい、今回のことといい、全体の秩序を乱すような者は要らん。うちは。一切要らん。」・・「何が監督署だ、何が裁判所だ。自分がやっていることを隠しておいて、何が裁判所だ。とぼけんなよ、本当に。俺は絶対、許さんぞ。」「会社がやっていることに対して妨害し。辞めてもらう、そのときは。そういう気持ちで、もう不用意な言動は一切しないでくれ。わかっているのか。わかっているのかって聞いているだろう。」
その後、同年6月21日には、雇用契約期間を1年とする「労働契約書」をXY間で取り交わしたが、同契約に際し、Y2はXの問題行動に対して注意喚起する必要があると考え、「就業規則の懲戒事由に該当する場合は、譴責以上の処分を下す」等と記載した覚書にXの署名捺印を求め、Xもこれに応じました。
またY社は携帯電話製造業務の終了に伴い、Xについても新たな移動先を検討する必要が生じたところ、従前の半導体製造業務は交代制勤務が多く、Xが家族介護のために希望する定時勤務に就くことは困難であったため、Y社はXを清掃業務が主たる目的とするK社に出向させ、同年7月11日よりY会社独身寮の清掃業務に就けることにしました。
同異動までに若干の間隔があいたところ(7月3日~同10日)、Y2はXに就かせる通常の業務がないことと、Xの問題行動に鑑み、次の職場でも問題を起こさせないためにも上記待機期間中、会社会議室において社内規程を精読するよう命じました。
また同年7月11日からXは出向先K社において、寮の清掃業務に従事していましたが、翌年の人事考課の際、3回の評価を行うところ、K社担当者による1次評価Bに対し、3次評価者であるY2は同評価をCとするよう修正依頼を行い、結果的に査定がCとなった結果、各月の基本給額はB評価と比べて3000円ほど低くなりました。
XはY1・Y2およびY社において上記一連の行為が不法行為にあたり損害を受けたと主張し、損害賠償請求を提起したものです。これに対して、1審ではYが「Xの言動に関する誤った理解を前提」に、上記一連の行為を行ったと認定し、これが「全体として、原告の勤務先ないし出向元であることや、その人事担当者であるという優越的地位に乗じて、原告を心理的に追い詰め、長年の勤務先である被告会社の従業員としての地位を根本的に脅かすべき嫌がらせ(いわゆるパワーハラスメント)を構成する」とし、慰謝料300万円をY等がXに支払うよう命じました。これに対して、Y及びY1・Y2が控訴したものです。
判決 控訴一部認容、一部棄却
「Xの中傷発言があったことを前提としても、本件面談の際のY1の発言態度や発言内容は、X提出のCD-Rのとおりであり、感情的になって、大きな声を出し、Xを叱責する場面が見られ、従業員に対する注意、指導としてはいささか行き過ぎであったことは否定し難い。すなわちY1が大きな声を出し、Xの人間性を否定するかのような不相当な表現を用いてXを叱責した点については、従業員に対する注意、指導として社会通念上許容される範囲を超えているものであり、Xに対する不法行為を構成するというべきである。」
「もっとも、本件面談の際、Y1が感情的になって大きな声を出したのは、Xが人事担当者であるY1に対して、ふて腐れ、横をむくなどの不遜な態度を取り続けたことが多分に起因していると考えられるところ、Xはこの場でのY1との会話を同人に秘して録音していたのであり、Xは録音を意識して会話に臨んでいるのに対して、Y1は録音されていることに気づかず、Xの対応に発言内容をエスカレートさせていったと見られるのである」「Y1の上記発言に至るまでの経緯などからすれば、その額は相当低額で足りるというべきである」
「原判決が認容する慰謝料額は相当な額であるとはいえない。以上の事情及び本件に顕れた全事情を総合勘案すると、上記行為に対する慰謝料は10万円とするのが相当である。」(なお上司Y1言動以外の一連の行為については、いずれも違法性がなく不法行為に該当しないと判示。)
パワハラの事実認定と法的評価について
原審・控訴審ともに、労働者側が秘密録音し、裁判所に提出したY1の言動は事実として認定されています。しかしながら原審・控訴審において判断が割れたのは、当該事実に対する法的評価です。原審は上記認定事実を基に、その後の会社側対応全てがパワハラに該当するとし、慰謝料300万円の支払いを命じた一方、控訴審は一転して慰謝料10万円の支払いに留めました。同相違はY1の言動に対する法的評価によるものです。
控訴審判決は本件Y1の言動自体は原審同様に「いささか行き過ぎ」「人間性を否定するかのような不相当な表現」とし、不法行為に該当することを認めますが、当該言動に至る経緯として次の点を挙げます。Xが「ふて腐れ、横をむくなどの不遜な態度をとり続けたこと」と秘密録音していた点です。当該経緯からみて、損害賠償額は「相当低額で足りる」としており、法的評価とりわけ損害賠償額の算定に際しては、「暴言」の事実関係のみならず、その経緯が極めて重要であることを明らかにするものです。
コメント
最近の同種裁判例として、パワハラ被害を主張する社員が、後日、会社に連絡し、先輩社員の謝罪発言を秘密録音した上で、当該音声記録をパワハラ事実の証拠として主張した事案がありました(東京地裁平成21.6.26 )。これに対し判決では「原告がいわば言質を取るために、録音することを相手方には知らせず、誘導的な質問をしているものである」とした上で、当該謝罪発言も「この通話全体を注意して聞けば、先輩社員は、原告からの電話を当初から迷惑に感じて、早く、これを切り上げようとして、原告の言うことに合わせて、形式的に「すいません」との発言をしたものにすぎないことは明らかであって、先輩社員が、この通話の当時、原告の言い分を認めていたものとは到底解されない。」とします(結論 請求棄却)。当該判断からも、裁判所は秘密録音を理由にただちに音声記録を証拠排除しない一方、慎重に当該記録の事実認定と法的評価を行っていることが伺われるものです。
著者プロフィール
北岡 大介
北岡社会保険労務士事務所
社会保険労務士